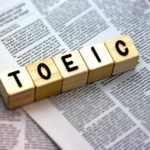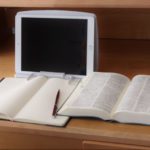学校教育における英語教育改革が進んでいます。
今までと大きく変わることは,小学校中学年で外国語が必修化,高学年で教科化されることです。
もちろん中学校,高等学校の学習指導要領も大きく改訂され,教えられる内容や指導方法も変わってきています。
この記事では特に,英語教育が小学校から重視されることによる中等教育(中学校・高等学校)での英語をとりまく環境への影響について考えていきます。
そもそも外国語の「必修化」「教科化」とは何か
今までも小学校の高学年では英語を学んでいました。
2002年以降ALT(外国語指導助手)の先生により、小学校でも英語に触れる機会が少しずつ増やされてきました。
しかしALTの先生の授業の成績は通信簿で評価されていませんでした。
正式な「教科」ではなかったためです。
しかし2020年度からは国語、算数、理科、社会と同様に「外国語」が正式な強化となり、通信簿で成績が評価されます。
これが、「小学校で英語が必修化される」こと意味です。
2019年度までは、決められた教科書などはなく,評価して成績をつける必要もありませんでした。
要するに,中学校から英語を学び始めるための準備期間として,楽しい英語の遊びなどを通して助走をつけるための「必修化」でした。
そして早期英語教育への機運がさらに高まり,もともと小学校高学年でやっていたこれらの内容が中学年にスライドし,高学年では「外国語」という授業として「教科化」されることになります。
「教科化」とは文部科学省の検定を通過した教科書を使用して授業を行い,成績評価もするということです。
今まで中学校から始まっていた内容が,小学校5年生から始まるということです。
小学校での「教科化」が中等教育へのどのように影響するか
学習する英単語の数が一気に増えます。
2020年までの学習指導要領では,中学校で約1200語,高校で約1800語を学び,中高6年間で3000語の英単語を,教科書を中心に学んできていました。
(もちろん,普通科高校では主に単語帳や模擬試験を通してそれ以上の単語に触れることになると思います。)
一方で新しい学習指導要領では,小学校で600~700語,中学校で1600~1800語,高校で1800~2500語を学ぶことが求められています。
最大で5000語となり,これは現行で学ぶ語数より2000語増えることになります。
ちなみに,小学校の「国語」で習う漢字が約1000,中学校でも1000強くらいだそうです。
「意味が分かる単語」と「使える単語」で分かれてくる
学習する語彙数が増えることにともなって注目されてきた概念が,「受容語彙」と「発信語彙」という考え方です。
「受容語彙」とは読んだり聞いたりして意味が分かる単語,「発信語彙」はそれだけでなく自分が書いたり話したりするときに使いこなせる単語という意味です。
中等教育では今まで「読む」「聞く」中心の授業で進められてきましたが,これからは「話す」「書く」ことも同じバランスで取り入れなくてはならず,一方で学習語彙数も増えるため負担が大きくなっています。
そこで「受容語彙」「発信語彙」という考え方にもとづいてそれぞれの単語の重要度や性質に合わせた覚え方に注目が集まっています。
実際にこの考え方に準拠した単語帳も複数出版されています。
授業のいろいろな場面で「4技能化」,入試の「難化」
「読む」「聞く」に偏った授業からバランスのよい授業に
「読む」「聞く」「話す」「書く」の4つの能力をバランスよく伸ばす指導ということは実は現行課程の学習指導要領から言われてきたことでした。
しかし入試が以前「読む」「聞く」メインなこともあって実態は「読む」「聞く」ばかりの授業でした。
また,日本の生徒は特に英語を「話す」ことに対して学習意欲が低いということも課題として挙げられていました。
小学校3年生に開始年齢が引き下げられることによって,音声中心で学習する期間を長く取れることとともに,ゲーム的な活動を楽しめなくなる(12歳くらいでしょうか)前に楽しく学ぶ機会を設けることができることも考えられます。
結果,大学の4技能入試が始まることも相まって,中等教育では「話す」活動に対する抵抗感が弱まることも予想されます。
思春期になってからみんなで英語を話し始めるとなんとなく恥ずかしいですが,小学校から英語を話す授業が当たり前だったらあまり抵抗がないということも理解できます。
高校入試における英語試験の難化
英語授業の開始年齢が2年引き下げられるわけですから,中学校3年生時点における求められる英語力も当然たかまるということです。
高校入試は中学校の学習指導要領に準拠して作成されますので,上で挙げた学習語彙の増加は数字で見て取れる難化要素になりうるでしょう。
すでに進学校と呼ばれる高校の入学試験においては,高校生でも知らない難単語が解答の鍵となるような問題も出題されたということもあるそうです。
まとめ
すべての小学校で3年生から英語の授業が始まることによる中等教育への影響について紹介してきました。
覚える単語の数の増加,「話す」「書く」内容の授業の増加,高校入試の難化を挙げてきましたが,目に見えないいろいろな部分で影響は出てくると予想されます。
一方で文科省の狙いは英語嫌いの子供を減らすことにもあると思いますので,小さいころから英語は勉強ではなく楽しいものだという認識をつけておくことが,中学から高校,その先に続く英語学習を乗り切るためには重要ですね。