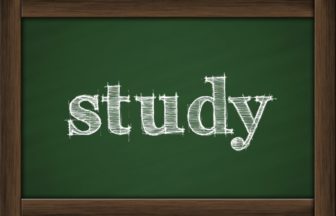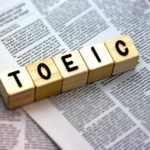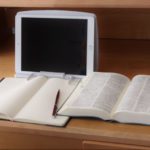2020年から小学校での英語教育が必修化・教科化され、英語教育に注目が集まり始めて久しく、学習指導要領の大幅改訂にともなった英語教育改革が進められ、色々な議論が交わされています。
今まで英語教育の中核をなしてきた場所は中学校と高校ですが、今回の英語教育改革出によってこの内容や、その先にある大学入試も大きく変わります。
この記事では中等教育においてどういったことが大切になってくるか、特に大学入試について考えていきたいと思います。
なぜ大学入試の英語の試験が大きく変わるか
大学入試改革は高大接続改革とも言われています。
今まで中学校や高校の学習指導要領では、「読む」「聞く」「話す」「書く」をバランスよく学ぶことが書かれていました。
しかし、皆さんもご存知のように大学入試は「読む」(と「聞く」)技能を測る試験が中心となっていて、大学によっては申し訳程度に「書く」試験を課す程度でした。
すると、真面目に学習指導要領に準拠して授業をするよりも、クラシックな文法訳読式の授業を展開した方が大学入試に強い生徒が育つことになります。
(もちろん、すべての学校でそういうわけではなく、超進学校と言われるところではしっかり4技能以上の授業をしている学校もあります)
学校は進学実績を作りたいので、「読む」「聞く」メインの授業をするようになり、結果として学習指導要領と実際の中学高校の授業内容に乖離が生まれてしまっていました。
それを是正するために、今度の大学入試改革では「話す」「書く」試験を取り入れることになりました。
入試で測られるのですから、学校の授業でもそれに合わせた授業にならなければなりません。
大学入試で「話す」「書く」能力を評価することの是非
大学入試に「話す」「書く」試験を導入する理由は上で紹介した通りです。
グローバル化が進む現代社会では英語を受信することだけではなく自ら発信できるようになる必要がありますから、中学高校の授業でもっと積極的にスピーキングやライティングを扱うようにするために入試改革をすることは筆者個人として賛成ですし、頼もしく感じています。
指導要領で4技能の伸長をうたっているのに、スピーキングの能力だけ評価されなかった今までの方が逆に矛盾しているという考え方もできます。
ただ、スピーキングの入試への導入には問題点も指摘されています。
それは、国の運営する大学入試センターや個々の大学が問題を作成するのではなく、民間企業に作成を委託することに集約されます。
国がスピーキングの試験を作成し、実施運営するにはノウハウと準備期間が無さすぎるという理由で外部に委託されることになりました。
具体的には、GTEC(ベネッセ)、英検、TEAP、TOEIC、TOEFLなどが試験を作成し、実施することになります。
それらはすべてCEFRという共通の英語力を表す指標を受験者に提示してくれますので、異なる試験を受けても同じように英語力を測ることができるということになっています。
細かい問題点は以下の通りです。
・テストの受験料が高額(裕福な家庭は何回も練習できる)
・テストの受験地が少ない(都市圏の生徒が有利)
・CEFRでは日本のすべての生徒をせいぜい3グループ程度にしか分けることができない。
・そもそも外部テストは使用目的が違うため、テストによって違う力が測られている。
・認定を受けた業者が発行する出版物が、高校現場で寡占状態になる。
これらのデメリットを高校と大学は懸念しています。このデメリットを承知でとにかくスピーキングテストを導入しないといけないという危機感を持っている人もいます。
メリットもデメリットも大きいことが、より議論を白熱させています。
一方で各民間企業はこのテストの開発に大規模な投資をしていますので、これはもうひっくり返すことは難しいところまで来ています。
大事なことは、民間試験に対応するために、中等教育段階でどういったことが重要になってくるか考えておくことです。
中学、高校の英語教育ではどんなことが重要か
「話す」「書く」試験の導入のための民間試験ですが、「読む」「聞く」試験の内容も今までとは変わってきています。
例を挙げると、「読む」試験では今までの説明型の文章とは違ってパンフレットや広告、メールなど、より実際の社会で読む機会が多いであろう形式の文章を読まされます。
しかもすべて読む時間は与えられていないと言っていいほど早く読まなければなりません。
中等教育においても、より実践的な文章を読んでおく必要があるでしょう。
「話す」試験では、音読、応答、意見陳述の力が測られます。
正しい発音をよく聞いて、英文は実際に口に出して読む習慣をつけることが必要です。
また、自分の思ったことを英語に直す練習は今までやられてきませんでしたが、これからは入試で必要になる能力です。
これらはすぐに身につく技能ではありませんので、中高6年間かけて意識するべきテーマになります。
まとめ
この記事では大学入試改革と民間試験のメリットとデメリット、そしてそれに対応するために中等教育で何を重要視すべきかを考えてきました。
色々な考え方がありますが、過去最大の改革と言っていいほど大きな変化ですので、これに対応できるかできないかで大きく変わってきます。
もちろん小学校から英語に慣れ親しんでおくことも、中学校からの英語の授業にうまく対応する上で重要なことかもしれませんね。