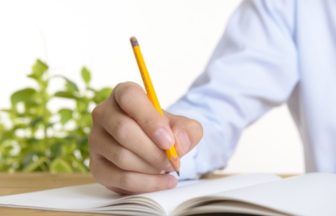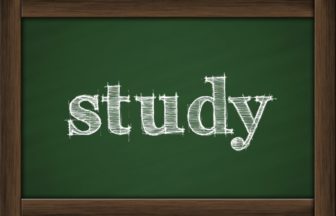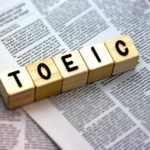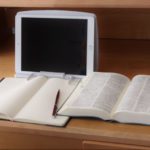学習指導要領の大幅改訂、大学入試改革(高大接続改革)、AIの発達による将来設計の難しさなど、教育業界は大きな変革のときを迎えています。
特に英語教育においては、大学入試にスピーキングや民間業者の試験が導入され、またAIによる自動翻訳の発達が英語学習の意義そのものを脅かすなど、様々な影響を受けています。
この記事では、英語教育をとりまくそれら外的な要因を超えて、「中学校・高校で意識して学ぶべきことは何なのか」を考察します。
中高生は何の目的のために英語を勉強するのか?
「受験に必要だから」英語を勉強している中高生
一部の英語が好きな生徒を除き、多くの中高生はこう思っているのではないでしょうか。
つまり、「センター試験で○○点です」とか「TOEICで○○点です」とかを公式に証明する権利と交換するために英語を勉強しているわけです。
そもそも勉強の目的は人によって様々ですから、この考え方の是非は問いません。
しかし、筆者個人としては何かと交換できることは本来の教育の過程で生じる残滓に過ぎないと感じています。
上で挙げたような数値で表せる能力は、AIによって簡単にリプレースされる能力だと思われるからです。
大学とその先のことは受験生にはなかなか分からない
今までのセンター試験では受験生の「思考力」や「判断力」をしっかり測れていませんでした。
そのため、「思考力」や「判断力」をしっかり測れない大学入試突破をゴールとしていた学校教育では、そのような能力はなかなか身につきませんでした。
その反省の意味を込めて、文科省は英語教育改革に踏み切っているわけです。
結果的に、「アクティブ・ラーニング」や「主体的・対話的で深い学び」という抽象的な目標が掲げられ、スピーキングやライティングなど数値化が難しい試験を入試に組み込もうとしています。
目の前の勉強に一生懸命な受験生本人には、「大学はゴールではなくスタートだ」ということはなかなか分からないことです。
英語教育改革の内容には賛否ありますが、教育現場に丸投げするのではなく、制度的に軌道修正しようという展開は非常に頼もしいものです。
中高生が本当に必要としている能力とはなにか
英語が使えるだけでは足りない
英語学習自体が重要であることについては、もちろん否定しません。
日本での英語教育はこれまで単語や文法を暗記し、入試問題で高得点取れることがゴールにされていました。
そのため、英語でコミュニケーションは取れなくても、読み書きの能力は高い人が結構いますし、難しい学術論文を英語で読み書きできる人も少なくありません。
しかしグローバル化が今後さらに進む社会では、「英語でコミュニケーションできること」が重要となり、当たり前となるような時代に突入していくでしょう。
かつての日本では、「読み書きそろばん」が出来れば「学がある」と評価されていました。
ですが現代日本社会では、できて当たり前ですよね?
同様に、英語で(読み書きのみではなく)コミュニケーションできることは、帰国子女や留学生等一部の人の「特殊能力」でしたが、今後はできないと恥ずかしい当然の能力になっていくでしょう。
高校までの英語教育の目標
高校卒業までに英語を自在に使えるようになっていれば、子供の英語教育は成功と言えるのではないでしょうか。
とはいえ、「英語を使えるだけ」の人材だと、遅かれ早かれAIや英語ができる海外からの移民に代替されてしまうでしょう。
ですので、学校教育では言語を学ぶことを通して、「情報を認知する力」「解釈する力」「相手を理解し、自分で考え判断する力」をきちんと身につけさせたいところです。
理想論にはなりますが、AI時代の到来が現実味を帯びてきた中、文科省も教育改革に本腰をいれています。
親もこれまでの子育てとは異なる教育方針に順応し、心して頑張らねばならない時代がすぐそこまで来ていると言えるのです。
具体的に何を意識すればよいか
従来は、大学入試等、試験で「正解」を解答できる能力を身につけるのが「英語教育」でした。
しかし上述の通り、単純に単語と文法の暗記で導き出すスキルはAIが得意とする分野になります。
今後、AIにとって替わらない人材になるには、自分で課題を見つけ、学んだことをもとに仮説を立て、他の生徒と協働しながら検証するという「アクティブ・ラーニング」が求められてきます。
これは英語に限ったことではありません。
「アクティブ・ラーニング」のために子供に意識させたいこととしては、日ごろから身近なことに「なぜ」の疑問を持って、「~だからだと思う」と仮説を立て、検証を重ねる習慣をつけることです。
例えば英語で言えば、come true「実現する」とかcome alive「生き生きする」などポジティブな意味にはcomeが使われ、go mad「気が狂う」とかgo bankrupt「倒産する」などネガティブなことにはgoが使われます。
「それはなぜなのか?」
単に英単語をやみくもに暗記するのではなく、言葉に意識を傾けて学習していくのです。
日本語で「今行くよ。」を英語で言うと、“I’m coming.”となるのはなぜだろうといったことも同様の疑問です。
人が気付かないような視点から課題を見つけ、それらを関連づける練習は、学校教育だけではなく、「幼少期から親の教育」でも身につけることができます。
親がいろいろな気付きを提案できるようアンテナを張り巡らせておくと良いですね。
まとめ
英語が使えることはこれからも重要な能力になることは間違いないですが、それだけですべて解決するという時代ではなくなってきています。
大学入試を突破することも重要なことですが、その先の大学卒業後、何を学んだら自分の力を活かすことができるのかということを自分で考えられるようになることも必要です。
そのためには受容した情報を自分なりに解釈し、課題を見つけていくということを目指して、学校教育や家庭の教育で感性を刺激する環境に置いてあげたいところですね。